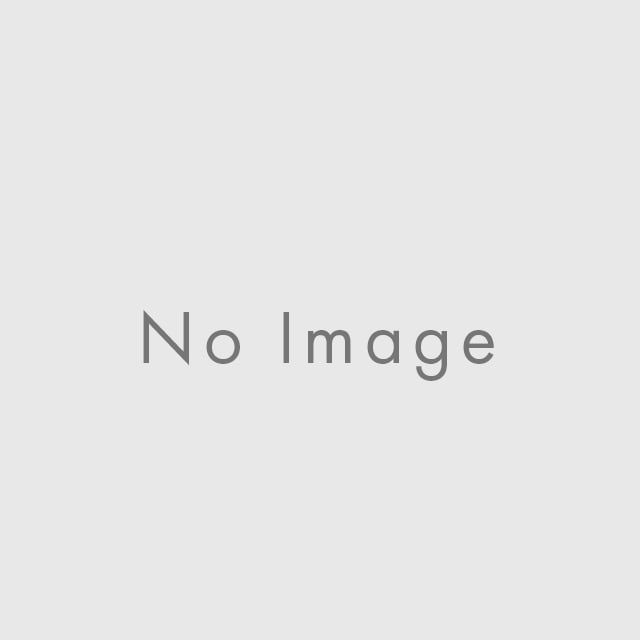マウスピース型矯正装置と歯科矯正用アンカースクリューに関する自分の見解を話したいと思います。
結論から言うと、マウスピース矯正を行う場合において歯科矯正用アンカースクリューはほぼ必須かと考えています。
よほど簡単なケースであればアンカースクリューは必要ありませんが、当院ではマウスピース矯正を患者さんに施術する場合殆ど全員使用しているかと思います。
ケース別で必要な理由を記載します。
①叢生(歯がガタガタしているケース)
叢生の原因としてスペース不足が考えられます。
スペース不足を解消するためには、①拡大②IPR、ディスキング③抜歯の3つの対応方法があります。
拡大とは歯列を拡げることですが、前歯を前に出す拡大は見た目や咬合の観点から適応が限られてしまいます。
前が駄目だとすると横、側方拡大もしくは後方拡大(遠心移動)になります。
日本人の骨の厚みは薄い場合が多いため、横・側方拡大も適応できるケースが限られてしまいます。
もしCTなどで歯槽骨の厚みを確認しないで側方拡大を行ってしまうと歯肉退縮や知覚過敏などの別の問題を誘発するリスクがありますので注意した方が安全です。
となると、最後に残るのが後方拡大・遠心移動になります。
そして、この遠心移動をマウスピース単独で行おうとするとなかなか上手くいきません、予測実現性が低くなります。
この結果は過去のたくさんの研究や論文などでも報告されており、エビデンスもあります。
そこで出番なのが歯科矯正用アンカースクリューになります。スクリューからマウスピースやボタンに顎内ゴム、結紮線などを使用して奥歯(大臼歯)を後方拡大・遠心移動を確実に行うことが可能(予測実現性が高い治療と言える)になります。
他にも奥歯のかみ合わせの調整などにも都合良く使用することが出来るので治療の精度が格段に向上します。
②上顎前突(出っ歯)
上顎前突の解決策は、①上の歯を引っ込めるもしくは②下の歯を前に出すの2つです。
どちらを選択するかは年齢、骨格の状態、歯の位置・角度、顔貌などから総合的に判断して決めます。
が、実際には上の歯を引っ込めることが殆どです。
上の歯を引っ込めるためにはスペースが必要になります。日本人の場合は抜歯(小臼歯抜歯)が多いです。
歯を抜いて前歯を引っ込める際に注意しなくてはいけないのが、ボーイングエフェクトとアンカレッジロスの2つです。
ボーイングエフェクトはワイヤー矯正でも生じますが、前歯と奥歯を引っ張り合うことにより歯列がたわんでくる現象をさします。
アンカレッジロスは意図せず奥歯が手前側にずれてしまう現象です。
この2つは抜歯矯正においては必ず考えなくてはいけない現象であり、矯正医を悩ます永遠の課題でもあります。
もちろんこれらに対する対策はいくつかありますが、その一つが歯科矯正用アンカースクリューとの併用になります。
上の歯が倒れて歯が挺出(歯がコントロールしきれずに伸びてしまう)のを予防・改善したり、奥歯が手前にズレるのを予防・改善したり色んな場面で有効的に活用できます。
③下顎前突(受け口)
上顎前突の逆の治療になります。
下の前歯を内側に引っ込めることが多いですが、日本人の症例では下の抜歯を選択することは少ないです。
抜歯の代わりに臼歯の遠心移動を行って、スペース作りや上下奥歯のかみ合わせの調整を狙います。
臼歯を遠心移動させる場合も同様にマウスピース単独では予測実現性が低いというエビデンスはたくさんあります。
そのために歯科矯正用アンカースクリューを奥歯の後ろや頬棚部、歯根間に設置することによって治療を行うことが出来ます。
④過蓋咬合
前歯の重なりが大きく、下の歯があまり見えない状態です。
治療としては①前歯の圧下②臼歯の挺出のどちらか、両方を行って過蓋咬合の解消を狙います。
これは上顎前突、下顎前突と異なり、上下的(垂直的)な問題になります。
マウスピース型矯正治療では垂直的なコントロールが苦手な部分でもあります、とくに挺出はマウスピース装置の形の上で難しいところがあります。
そのため実際の治療では前歯の圧下を行うことが多いかなと考えています。
前歯の圧下を行う際にも歯科矯正用アンカースクリューを併用して直接前歯に力をかけることで効率的に前歯の圧下を達成することが可能になります。
④開咬
過蓋咬合の逆になります、垂直的な問題でもあります。
アプローチとしては①前歯の挺出②臼歯の圧下になります。
この臼歯の圧下はマウスピース装置の形の特性上、歯を上から覆う形であること+普段の奥歯の噛む力が合わさって自然に約0.5-1.0mmは自然に圧下されることが多いです。
そのため、マウスピース矯正と開咬の治療は非常に相性が良いです。
但し、これも開咬の程度によります。
臼歯の圧下量が大きく必要な症例ではやはりマウスピース単独では難しいため、奥歯の外側や内側にアンカースクリューを埋入して臼歯の圧下を積極的に行わないと開咬の解消は難しいかと思います。
以上のように、ほとんどの不正咬合の治療において有用性や親和性が確認できたかと思います。
今回はここまでになります。